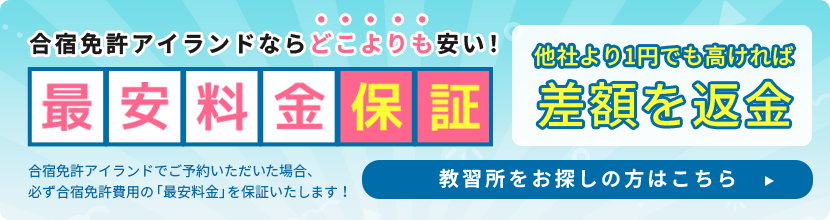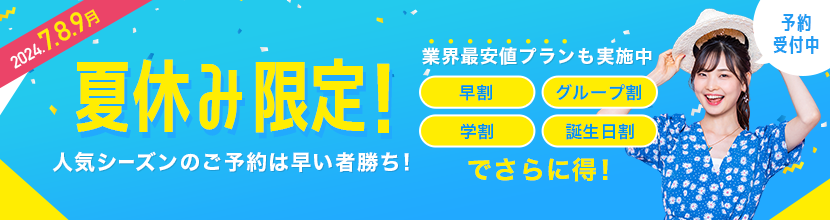免許取得までもう一息!教習所の第二段階ではどんなことをやる?

運転免許を取得するためには、教習所で「第一段階」と「第二段階」の2つのステップをクリアする必要があります。第一段階で基本的な運転操作や交通ルールを学び、仮免許試験に合格した後は、第二段階教習が始まります。第二段階ではより実践的な運転技術や安全運転の知識を深めることが求められます。
今回は、教習所での第二段階の内容について詳しく解説します。
第一段階について知りたい方は「免許取得の第一歩!教習所での第一段階ってどんなことをやってるの?」もあわせてご覧ください。
技能教習は、路上教習などより実践的に

仮免許を取得すると、条件付きで公道を運転できるようになります。そのため、第二段階教習では、路上教習が始まるところが大きな変化です。
第二段階の技能教習では、一般道路や高速道路を実際に走る路上教習や、教習場内で運転スキルの向上や危険察知について学ぶなど、第一段階と比べ、より実践的な運転テクニックを学びます。
路上教習
仮免許取得後の第二段階教習では、路上教習が始まります。
第一段階の技能教習で使用していた場内コースでは、自分と同じように免許を取ろうと勉強している運転者しかおらず、走行速度も遅いです。しかし、路上には当然一般の運転者もいます。場内コースでの技能教習のように急な減速や停車はできません。さらに実際の道路では、交通量の多い道路や住宅街、狭い道、信号のない交差点、見通しの悪い道などさまざまなシチュエーションでの運転を経験することになります。路上教習を通して、どんな状況でも安全運転できるようスキルを身につけならなければなりません。最初は緊張すると思いますが、公道でもスムーズに自動車を運転するため、落ち着いて学びましょう。
路上教習では、第一段階と同じく助手席に教官が乗っています。誤った運転や危険な運転をした場合には、どのような部分が誤っていたのかをその都度説明してくれます。しっかりと説明を聞き、運転技術向上に努めましょう。
高速道路教習
第二段階の技能教習では、高速道路を実際に走行します。高速道路での運転は一般道とは異なり、特有のルールや走行方法があります。高速道路の合流や車線変更、適切な車間距離の取り方などを学びます。
教官と生徒二人が車に乗り、行きは一人目、途中のサービスエリアで交代して、帰りは二人目の生徒が運転することが多いです。生徒一人の場合は、行きも帰りも一人で運転します。また、教習所によってはシミュレーターを使用する場合もあります。
関連記事:高速教習に臨もう!
場内教習も続く
第二段階では路上教習が始まりますが、これまで通り場内での教習も行います。場内コースでは、縦列駐車と方向転換を学びます。どちらも自動車を運転する上で必要な技術です。この2つは習得が難しいと言われているため、何度も練習することになるかもしれません。卒業検定でもチェックされる技術なので、教習の段階でしっかりと身につけておきましょう。また、路上教習を行っていると自分の苦手な操作が見つかることもあります。苦手な操作は場内コースで何度も練習しましょう。その努力が上達へとつながります。
加えて、第二段階では「急ブレーキ教習」も重要なカリキュラムの一つです。急な飛び出しや予期せぬ危険に対処するために、適切なブレーキのかけ方やハンドリングを学びます。スピードを出して走行している時に、急ブレーキをかけてから車が停まるまでどの程度距離が必要なのか、急ブレーキの際の車両の挙動を体感する教習です。
学科教習では、危険予測や応急救護を学ぶ

第二段階では、技能教習と並行して学科教習も引き続き行われます。第一段階の学科教習では、車や運転の基礎について学びましたが、第二段階では応用知識を学びます。実際に自動車を運転する際に必要な知識を正しく身につけましょう。
学科教習の中で行う、座学以外のカリキュラムについて紹介します。
危険予測ディスカッション
車の運転には様々な危険が伴います。道路上にはたくさんの自動車が走っているだけでなく、歩行者や自転車、バイクもいます。危険性を考えずに車を運転していると、重大な事故を起こしてしまうかもしれません。事故を防ぐためにも「もしかしたら」と危険を予測した運転が大切です。
第二段階では、自動車運転の危険性についてディスカッションをする授業があります。危険予測ディスカッションは、教習所に通う生徒2、3人と教官が一緒に自動車に乗って行います。生徒が交代して自動車を運転し、運転していない生徒は運転している生徒の運転をよく観察します。その後「それぞれの運転に危険は無かったか」ディスカッションを行います。自分の運転が安全なのか、自分ではよくわからないことも多いです。別の生徒から指摘されることで気づくこともあるでしょう。生徒同士で指摘し合い運転技術を高めることが、この危険予想ディスカッションの目的です。
単に運転技術を身につけるだけでは交通事故を防ぐことはできません。自分が交通ルールを守って運転していたとしても、他の自動車や歩行者が安全に運転・歩行しているとは限りませんし、お互いがルールを守っていても道路の条件が悪ければ事故が起きてしまうかもしれません。そのため、「もしかしたら曲がり角から人が飛び出してくるかもしれない」「見通しが悪い場所では、死角に車がいるかもしれない」など、危険を予測することが重要です。第二段階では、シミュレーターや実際の運転を通じて危険を事前に察知し、安全な行動を取る訓練を行います。
応急救護
自動車を運転する以上、交通事故を起こしてしまう可能性は捨て切れません。対人事故を起こし、相手が重大な怪我をすることも考えられます。事故を起こしてしまった場合、動揺したり焦ったりしてしまうかもしれませんが、まずは被害者の救助のため、周囲の人と協力して適切な救護を行わなければなりません。
応急救護教習では、交通事故が発生した際の適切な対応方法を学び、負傷者の応急処置や救急車を呼ぶ際の手順を習得します。AEDの使い方や心肺蘇生法など、実際の救護場面で役立つスキルを身につけます。応急救護の仕方を身につけていれば、万が一事故が起きてしまったときに人命救助ができるので、この教習を通していざというときに備えておくことが重要です。
第二段階が終わると、卒業検定へ

第二段階をクリアした後は、いよいよ卒業検定を受けます。卒業検定では、実際に路上での運転技術や交通ルールの遵守、危険予測能力などが評価されます。無事に合格すれば教習所を卒業し、本試験を受ける準備が整います。
卒業検定合格後は、運転免許試験場で学科試験と適正検査を受けることになります。この学科試験・検査に合格することで、正式に運転免許証が交付されます。学科試験は交通ルールや安全運転に関する知識が問われるため、事前にしっかりと勉強しておくことが大切です。卒業検定について詳しく知りたい方は、「卒業検定とは?検定内容と、合格のためのコツや気をつけることを解説!」も併せてご覧ください。
まとめ:第二段階で実践的な知識・技術を身につけよう!

今回は、教習所における第二段階の学習内容についてご紹介しました。
第二段階では、第一段階に比べて学ぶことが多くなります。内容がより実践的になり、公道に出て一般車両と一緒に運転することになります。路上での運転は、初めは不安や緊張があるかもしれませんが、免許取得への大きな一歩です。
そして、第二段階を終えて卒業検定と運転免許試験場での試験に合格すれば、晴れて免許取得となります。焦らず、しっかりと準備をして臨みましょう!
合宿免許アイランドでは、合宿免許を受け入れている全国各地の教習所をご紹介しています。合宿免許を探すならアイランドで!
▼免許の種類から合宿免許を探す
https://www.ai-menkyo.jp/school/
運転免許取得をお考えなら最安料金を保証する
合宿免許アイランドにお任せください!