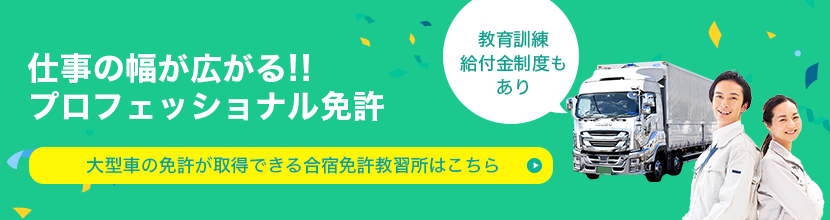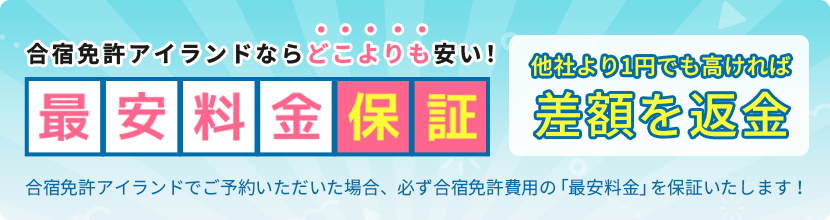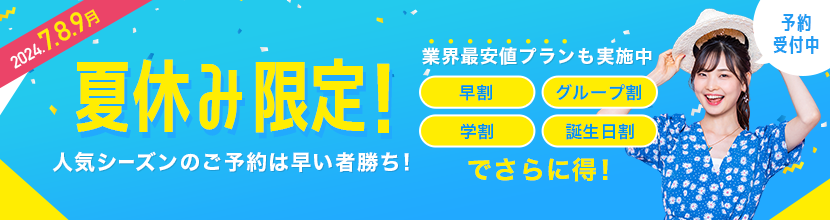牽引免許とは?取得条件と種類、おすすめの取得方法を徹底解説!

道路を走行しているときに、大型トレーラーやトラクターを見かけたことはありませんか?これらは牽引(けん引)車と呼ばれる車両で、運転するにあたって特別な免許が必要です。牽引車は運送業や物流業で使用されることが多く、牽引免許を取得しているとそれらの業界へ就職する際に有利になります。
ただし、一般的な普通自動車免許や二輪免許と異なり、牽引免許は取得条件が複雑です。そこで、今回は牽引免許が使える場面や種類、取得するための条件について詳しく解説します。
牽引免許とは?

牽引免許とは、牽引装置を持つ車両で、車両の総重量が750kgを超える車両(重被牽引車)を牽引するときに必要な免許です。貨物車両の一種で、引っ張る側の車両は牽引車(トラクター)と呼び、引っ張られる荷台や自走できない車両は被牽引車(トレーラー)と呼びます。牽引免許が必要な車両として、具体的にはタンクローリーやダンプトレーラーなどが挙げられます。また、総重量が750kgを超えるキャンピングカーや、空港で飛行機を移動させるトーイングカーなどを運転するときにも牽引免許が必要です。
牽引免許がなくても牽引できる場合
ただし、被牽引車の総重量が750kgに満たない車両の場合は、牽引免許を必要としません。車両の総重量は、被牽引車の車両重量+最大積載量の合計であり、これが750kgを超える場合は牽引免許が必要です。そのため、レジャーで使用するボートやキャンピングカーならばそこまでの重さがなく、牽引免許がなくても運転できるケースは多いでしょう。
また、総重量が750kgを超える場合でも、故障車をクレーンや牽引ロープなどを使って牽引する場合も、牽引免許がなくても運転することができます。ただしこの場合、故障車にはその車を運転できる免許を持つ人が乗り、ハンドル操作をしなければなりません。
被牽引車が750kgに満たない場合、普通自動車免許をはじめ、牽引車を運転するのに必要な免許だけで運転することが可能です。大型車で牽引するならば、大型免許が必要になります。
牽引するには、牽引する車の免許+牽引免許が必要
総重量が750kgを超える車両を牽引する場合、牽引車の運転免許+牽引免許が必要です。牽引装置は「普通自動車・準中型自動車・中型自動車・大型自動車・大型特殊自動車」についているため、牽引するためには、まずは上記いずれかの免許が必要です。
そして、大型車を扱う運送会社などでは、牽引免許の他に大型免許も持っていれば、就職が有利になる場合が多いです。牽引免許を必要とする職種であっても、入社するときに免許が必須というところばかりではありません。入社してからの免許取得制度が整えられているところもあります。しかし、入社前に必要な免許を持っていれば即戦力になるため、有利になることは間違いないでしょう。
牽引免許には3種類ある

牽引免許の種類は1つではありません。「牽引免許」「牽引二種免許」「牽引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)」の3種類があります。どんな車両を牽引するのかによって必要な免許が変わるため、それぞれの免許の違いを把握し、どの免許が必要なのかを把握しましょう。
牽引免許(第一種免許)
牽引免許は、車両総重量が750kgを超えるトレーラーなどの被牽引車を連結して引っ張り、公道を走る際に必要となる免許です。運送会社などが所有している「貨物トレーラー」を連結した車両などが例のひとつで、さまざまな荷物を積んで運搬しており、街中や高速道路でもよく見かけます。
牽引二種免許
普通自動車の二種免許がタクシーや路線バス、観光バスなどを運転するときに必要なのと同様に、牽引二種免許は、営業用途で使われる車両を牽引する際に必要な免許です。タクシーやバスのように車両が一体型になっている車両ではなく、運転席と客席が分離している車両を運転する場合に牽引二種免許が必要です。例えば、トレーラーバス(連結バス)のような車両です。国内ではまだそれほど多くありませんが、観光地などで増えつつあるため、観光業界で運転手として働きたい場合は、取得すると業務の幅が広がるでしょう。
牽引小型トレーラー限定免許(ライトトレーラー免許)
牽引小型トレーラー限定免許とは、連結する被牽引車両の総重量が750~2,000kg未満に限定された免許です。一般的にはキャンピングトレーラーやボートトレーラーなどの小型トレーラーを牽引することが多く、それほど重いものを引っ張ることができません。そのため、正式名称ではないものの「ライトトレーラー免許」と呼ばれることもあります。
注意点として、運送会社が所有しているような貨物トレーラーなどの場合、総重量2,000kgを超えることが多いです。運送会社などに就職し、物流関係の仕事に従事したい場合は、1つ目の牽引免許を取得しましょう。
大型車で牽引する場合は、大型免許も取る必要がある

牽引免許には「大型牽引免許」のような、特定の大きさの車両に絞った免許はありません。「牽引小型トレーラー限定免許」が総重量750~2,000kg未満の小さめの車両を対象としている免許であるため、実質的には、牽引免許が2,000kgを超える大型の被牽引車を牽引できる免許ということになります。
ただし、牽引免許があれば、それだけで大型の牽引車に乗れるというわけではありません。実際に大型の牽引車を運転するためには、大型免許と牽引免許の両方を取得している必要があります。
例えば、大型一種免許+牽引免許を取得すれば、普通一種から中型一種、大型一種までさまざまな大きさの車両はもちろん、タンクローリーや大型トレーラーまで幅広く運転することが可能です。そのため、物流業界などでは大型免許と牽引免許の両方を所有していることが、就職する上で強みになるでしょう。
牽引免許の取得条件

牽引免許を取るためにはいくつかの条件があり、すべて満たしている必要があります。普通自動車免許よりも厳しい条件があるため、免許を取得する前に条件を確認しておきましょう。
| 年齢 | 18歳以上 ※牽引二種免許では、21歳以上 |
|---|---|
| 取得免許 | 普通免許、中型免許、準中型免許、大型免許、大型特殊免許、第二種免許のいずれかを取得していること
※牽引二種免許では、「普通免許、中型免許、準中型免許、大型免許、大型特殊免許のいずれかを持っており、かつ取得してから3年以上経過している」または「他の二種免許を持っている」 |
| 視力 | 両眼で0.8以上、片眼では0.5以上が見えていること(眼鏡等可) |
| 深視力 | 三棹法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、平均誤差が2cm以下であること |
| 色彩判別 | 赤・青・黄が識別できること |
| 聴力 | 10m離れた距離で90デシベルの警告音を聞き取れること(補聴器により補われた聴力を含む) |
視力・深視力・色彩判別・聴力は、適正検査でチェックされます。
参考:けん引免許試験(指定教習所を卒業された方) | 警視庁
参考:大型特殊二種・けん引二種免許試験(直接試験場で受験される方) | 警視庁
参考:適性試験の合格基準 | 警視庁
牽引免許の取得方法は3種類

普通免許や大型免許、二輪免許などの試験を受けるときは、学科試験と技能試験があります。しかし、牽引免許では学科試験がありません。牽引免許を取得するには基本的に普通免許や大型免許などを取得していることが条件になっているため、すでに運転に必要な知識は持っているからです。
牽引免許を取得するには、技能教習12時限(第1段階5時限+第2段階7時限)を受ける必要があります。学科教習が無い分、普通自動車免許を取得するよりも短い期間で取得が可能です。教習所に通い卒業検定に合格した後、免許センターで適正試験に合格したら免許を取得できます。
牽引免許を取得する方法は、「教習所に通う」「合宿教習に参加する」「試験場での一発試験に合格する」という3つの方法があります。以下では、それぞれの方法について解説します。
教習所に通う
1つ目は教習所に通う方法です。自宅や学校、職場から近い教習所に通い、運転技術を身につけます。仕事をしながらや学校に通いながらでも、自分のペースで学ぶことができます。一方で、自分で教習の予約を取る必要があるため、教習所が混む夏休みや春休みの時期は希望通りに教習を受けられない場合があります。また、あらかじめスケジュールが組まれている合宿免許と比較すると、免許取得までに時間がかかる傾向にあります。
自分のペースで免許を取得したい人や、自宅から近い教習所で取得したい人、仕事や学校の合間に通える人におすすめです。
合宿免許に参加する
合宿免許とは、教習所が指定する宿泊施設に泊まりながら短期間で免許を取得する方法です。教習所が組んだカリキュラムに沿って教習が進むため、効率的に免許を取得でき、最短6日〜で牽引免許を取ることができます。合宿免許の場合も卒業後の流れは通学と同じで、免許センターでの適性試験に合格後、牽引免許を取得できます。
また、前述の通り牽引免許を取得するためには、牽引する車両の免許も必要です。大型の車両で牽引する場合は、牽引免許と大型免許の両方を取得していなければなりません。合宿免許では、牽引免許と他の車種の免許(大型免許など)を同時に取得できるプランを設けている教習所もあります。仕事の都合などで「どちらも一緒に取りたい」と考える人は、同時に教習を受けられるプランで効率的に免許を取得しましょう。
時期や教習所にもよりますが、合宿免許の費用は、教習費用・宿泊費・食費込みで計算すると通学よりも安く抑えられることが多いです。その一方で、合宿免許は教習期間を合宿先で過ごす必要があるため、まとまった休みを確保する必要があります。合宿免許は、費用を少しでも抑えたい人や、スケジュールの都合がつけられる人におすすめです。
取得したいご希望の車種、様々な条件をお伺いして最適な自動車学校様をご紹介致しますのでお気軽にお問合せください
通話無料ダイヤル:0120-727-659
LINE: 友だち追加
試験場での一発試験に合格する
一発試験は、教習所に通わず、運転免許センターで適性検査と技能検定を直接受験し、合格すすることで免許を取得する方法です。この場合、教習所に通ったり合宿免許に参加したりする必要がないため、費用と時間を節約することが可能です。
しかし、運転席と荷台や客車が分離している牽引車は、普通車や大型トラックなどとは異なる運転技術が必要です。難易度が高く、一回での合格はかなり難しいと言われています。
そのため「一発試験に何度も挑戦した結果、受験費用がかさんでしまった」ということになりかねません。確実に合格するためには、教習所に通う、または合宿免許に参加することをおすすめします。
牽引免許の試験内容と合格基準

牽引免許の技能試験では、主に以下の項目がチェックされます。
・右左折
・目標物に合わせた停車
・踏切通過
・指示速度での走行
・S字走行
・方向転換
これらのチェック項目については、普通免許や大型免許などを取得済みで、普段から運転をしている人ならば特に目新しいことではないかもしれません。しかし、普段の運転は難なくできていても、試験では試験官にも分かるようにしていなければ、減点されることもあり得るので注意しましょう。また、試験では乗車してから降車するまでの間しっかりチェックされています。試験を受けるコースでは横断歩道や信号のない交差点、見通しの悪い交差点などもあります。発進時や前方・後方・左右の安全確認、左右の巻き込み確認などの動作はもちろん、乗車するときや降車するときの動きも試験官に見られている意識を持ち、はっきりとした動作で行いましょう。
試験では100点満点から減点方式で採点され、最終的に70点以上(二種免許の場合は80点以上)あれば合格です。
まとめ:牽引免許の基本を押さえて、牽引免許を取得しよう!

牽引免許には3つの種類があり、それぞれの免許で運転できる車両の範囲が変わってきます。そのため、自分がこれから就きたい職業や、運転・牽引したい車両で必要な免許がどれなのか、はじめに把握しておくことが大切です。加えて、牽引する場合は牽引免許だけでなく、運転する車両の免許も必要です。大型車両で牽引する場合は、大型免許と牽引免許の両方を取得していなければなりません。
牽引免許を取得するときは、まず「いつまでに」「どの牽引免許と」「どの車両の免許が」必要なのかを明確にしましょう。その上で、免許取得に必要な費用・期間を理解して、スムーズに免許を取得できるように計画を立てることが重要です。
また、企業が「未経験者を採用するにあたって、入社後に免許を取得してもらいたい」と考えている場合にも、短期間で免許を取得できる合宿免許がおすすめです。こちらの「法人向け合宿免許を社員の免許取得で利用するメリット、免許費用についてご紹介」の記事もあわせてご覧ください。
合宿免許アイランドでは、牽引免許をはじめ、様々な免許が取得できるプランをご紹介しています。合宿免許を探すならアイランドで!
▼免許の種類から合宿免許を探す
https://www.ai-menkyo.jp/license/
運転免許取得をお考えなら最安料金を保証する
合宿免許アイランドにお任せください!